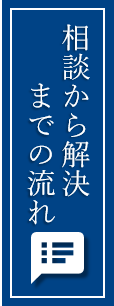【弁護士が解説】職務怠慢・業務怠慢な問題者員を処分する手続きと注意点を解説
目次
仕事をきちんと行うことは当然の義務
会社が従業員に対して給料を支払うのは、いうまでもなく、従業員がきちんと仕事をしたからです。従業員は、会社に対して、働いた分だけ給料を請求する権利があるのと裏返しとして、労働契約に基づいて、きちんと仕事を行うべき義務を当然に負っています。
したがって、きちんと仕事をしない職務怠慢は、会社としても厳しく注意すべきことがらであり、見過ごすべきではありません。とりわけ遅刻や欠勤は、その間、全く働いていないことになりますから、交通事情や急病など、やむを得ない事情がない限り、会社として改善指導を求めることに、何ら躊躇する必要はありません。
もっとも、我が国の労働法では、「働く」ということは「成果を出す」ことではなく、「勤務をすること」そのものであるととらえています。そのため、一応出勤はしているものの、仕事自体を熱心に行わないという従業員の場合は、「勤務している」という形式的な実態さえあれば、会社として、その働きぶりに満足がいかなくとも、労働契約で約束した給料を支払わざるを得なくなります。
こうした不釣り合いな事態が生じないよう、職務怠慢な従業員に対しては、その事実を見過ごすことなく改善指導を行い、場合によっては懲戒処分も活用しながら、対応していくことが必要不可欠となります。
職務怠慢な従業員とはどういう従業員なのか
職務怠慢な従業員が会社にとって望ましくないことはいうまでもありません。では、遅刻や欠勤が頻繁にあるわけではなく、毎日出勤してきているのに、職務怠慢な従業員であると評価する場合があるのはどうしてでしょうか。
たとえば企画職や営業職など、仕事の成果が形になるような職種の場合には、比較的、その熱心さを推し量りやすいといえます。しかし、事務職や管理職のように、働きぶりが明確な形になって表れにくい職種の場合は、ともすれば評価する者の主観によって左右されがちです。持ち場を離れたり、手が頻繁に止まっているなど、文字通り、怠けていることが目に見えれば別ですが、そうでもない限り、まがいなりにも仕事をしているように見える従業員であれば、熱心に仕事をしていると評価するのが普通の考え方です。
近時、テレワークが普及しつつありますが、他方でその広がりは頭打ちになっているともいわれています。その理由の一つに、従業員同士のコミュニケーション不足がいわれており、人事労務管理の観点からは、「働いている様子が見えない」問題として指摘されています。
従来、職務に熱心かどうかは、「見ていればわかる」といわれることがよくありました。しかし、部下の働きぶりを評価するのが上司といえども、一人の従業員の働きぶりを一から十まで見ているわけではありません。従来型の評価方法では、結局のところ、上司との付き合い方が上手な従業員が高評価を受けるという傾向にあり、実際にその従業員がどういう働きをしているかについては、意識的に目を向けていない傾向があったといわざるを得ません。
最近では、こうした評価の仕組みに対する見直しが進んでおり、抽象的一般的な働きぶりではなく、個別具体的な目標達成を評価しようという動きが見られます。その前提として、会社として、まず望ましい従業員像を確立することが重要であり、その水準に達しているかどうかで、従業員の仕事ぶりを図るという方向性が模索されています。
こうした観点から考えたとき、熱心な働きぶりとは、目標達成のためにどのような行動をしているかという点によって評価されることとなり、会社が考える望ましい従業員像を目指した働き方をしていない従業員の働きぶりをもって、不熱心と評価することになります。
問題社員を放置すると取り返しがつかないことに
職場の人間関係がどんどん悪くなる
問題社員の多くは、他の従業員とも折り合いが悪く、職場の雰囲気を悪くさせることがめずらしくありません。しかし、当の問題社員自身は、ほとんどが「自分は悪くない」と心の底から思っているので、現に他の従業員との関係が悪くても、それは相手の方に責任があると思い込んでいます。そのため、自分の行動を振り返って改めることはほぼ期待できず、他の従業員との関係もますます悪くなっていきます。
問題は循環し続ける
こうして職場の雰囲気を悪くさせている問題社員がいるにもかかわらず、事実上、放置している状態になると、当の問題社員はますます「自分は悪くない」という考えを強く持つようになり、その結果、他の従業員との関係もますます悪くなっていきます。こうなると、他の従業員も会社に対して不満を持つようになり、体調を崩してしまったり、耐えかねて退職してしまったりすることもあります。どうにか現場が回っているように見えても、実際は一人の問題社員のために他の従業員がそろって我慢をしているにすぎません。問題社員を放置すると、有用な人材の流出につながる深刻な事態に至りかねません。
職務怠慢な問題社員への注意指導の方法
まずは注意指導
職務怠慢な問題社員は、「いつか全うに働いてくれるようになるかもしれない」と見守っていたところで、まず改善することはありません。それゆえ、言って聞かせる必要がありますが、その方法にはいくつか押さえておかなければならないポイントがあります。
まず、最初は文字どおり、「言って聞かせる」こととして、口頭の注意でも構いませんが、それで改まらないならば、「注意指導書」を作成して交付すべきです。書面で注意指導をすることは、それなりに重みがありますし、何よりも実際に注意をしたということの証拠として後々重要になるためです。
この注意指導書は、
① いつ、どこで、誰が何をしたのか。
② その結果、業務上、どのような支障が生じたか。
③ これらの行為が、就業規則等の社内規程のどういう事項に違反するのか。
④ 今後、どのように改めるべきなのか。
といったことがらを、漏れなく具体的に記載することが必要不可欠です。特に、業務上、どのような支障が生じたのかを具体的に書くことが重要です。職務怠慢な従業員がいると、職場の雰囲気が悪くなったり、士気が下がるということはあると思いますが、そういうことを指摘しても十分とはいえません。なぜなら、職場の雰囲気や士気などは、人それぞれの「感じ方」が違うので、当の問題社員に「自分はそうは思わない」と言われてしまえばそれまでだからです。
この業務上の支障とは、目に見える不具合のことをいい、たとえば取引先からクレームが入ったであるとか、連絡不行届で危うく納期を過ぎてしまうところだったなど、後日に「こんな出来事があった」と説明できる内容を示すことが必要であると心得てください。
改まらない場合は懲戒処分
真っ当な社会人であれば、職務怠慢が問題であることは、注意されなくともわかることといえます。その裏返しとして、実際に職務怠慢な従業員は、そういう意識がないから職務怠慢なのであって、注意指導を繰り返し受けても態度が改まることはあまり期待できません。
何度か注意指導を繰り返しても、態度が改まらないような場合には、就業規則の定めに則って、懲戒処分を行うべきです。しかし、いきなり重い処分を行うことは禁物ですし、就業規則の定めから外れた処分を行うことはできません。けん責や戒告などの定めがあれば、まずはそこから処分を行い、それでもなお態度が改まらないなら、段階を践んで、懲戒処分を重ねていくべきこととなります。
なお、こういう問題社員に対して、始末書の提出を求めるという方法がとられることがよくあります。一方で、けん責や戒告の内容にも始末書を提出させることが規定されている場合、懲戒処分としてではなく、通常の注意指導として始末書の提出を求めると、本来、懲戒処分として行わなければならない対応を、正式な手続を践まないで行ったという議論になる場合があります。始末書の提出は、軽々に要求すべきではありません。
解雇の前に退職勧奨
こうして注意指導を繰り返し、さらには懲戒処分を行ったにもかかわらず、どうにも態度が改まらないという場合には、いよいよ会社を辞めてもらうということが視野に入ります。とても回りくどいことですが、我が国の労働法制は、従業員に辞めてもらうためのハードルがとても高く、雇い主が散々手を尽くしたけれどもどうにもならなかった、ということが証明できなければ、従業員が解雇が不当だと争えば、解雇はたちまち無効となってしまうことも少なくないのです。
ここまで問題が多い従業員だと、雇い主側から引導を渡して、辞めさせたいというお気持ちもごもっともです。しかし、実際に法律上は解雇のハードルが高い以上、そういう危ない橋を渡ることで、かえって問題社員の言い分が通ってしまうようなことがあっては本末転倒です。
そこで解雇にこだわることなく、こちらは解雇を考えているけれども、この際、自分から身を引く気持ちはないかどうかを話し合うという方法をワンクッション置くことが理想的です。ここまでで注意指導を繰り返して、懲戒処分も重ねていたならば、さすがに本人も自ら雇い主側からいよいよ声がかかれば、退職届を自分から提出することも期待できるかもしれません。
こうした退職勧奨を行うことそれ自体は、話し合いの範囲のことですので、それだけでハラスメントだといわれたり、損害賠償の対象になったりするものではありません。しかし、本人が退職しないという意思を固く持っているような場合に、しつこく退職勧奨を繰り返してしまうと、それは度が過ぎているということで、問題になることもあります。退職勧奨は、短期に決着がつかなければ、長々と繰り返しべきではないといえます。
職務怠慢であっても解雇には法的リスクを伴います
問題社員は、当の本人に自覚がない場合がほとんどであり、会社側からの注意指導に素直に従わない例が多く見られます。その結果、さらに問題社員化が進んだり、裁判所に訴え出たりすることも珍しくありません。
職務怠慢は多くの会社の就業規則では、懲戒事由として掲げられていますが、懲戒解雇事由とまでなり得るかは、職務の内容によってかなり限定的です。普通解雇とする場合でも、その職務怠慢がいかに会社にとって害悪となったかを客観的な証拠により、具体的に立証することができなければ、解雇は無効とされてしまう可能性が高いといえます。
また、裁判例の傾向では、一度、職務怠慢で注意指導を受けたとしても、これを反省して改善する可能性があるとの価値観により、過去に注意指導歴がないにもかかわらず、直ちに解雇とした場合には、その有効性が認められる例はほとんどないといえます。
一方で、従業員による職務怠慢が、会社にとって見過ごしてはならない従業員の問題行動であることは間違いありません。具体的な対応について、どのようなタイミングで、何を根拠として、どういった手順を踏んでいくべきか、当事務所がサポートさせていただきますので、お困りの際には是非ともご相談ください。
問題社員対応へのサポートについて
能力不足やパフォーマンスが低い従業員は、自分自身の仕事ぶりが評価されていないことの自覚がない場合が多く、会社が厳しい対応をとった場合には、強く反発される例がよくあります。こうした従業員を問題社員として対応する前、まず会社の方が、その従業員の能力不足等により、どういう害悪を被っているのか、冷静に分析することが必要です。
その上で、裁判例の傾向をふまえ、まずは問題状況の改善に努めるように指導し、その際には、会社が主観的に好ましくないと思っているだけではなく、客観的かつ具体的な根拠で、その従業員の能力不足等により、会社に害悪が生じていることを示すことが重要です。
こうした指導は、一回で効果が現れるものではなく、状況に応じて繰り返すことが必要であることも少なくありません。どのようなタイミングで、どういった内容の指導を行うべきかについて、当事務所でサポートさせていただきますので、是非ともご用命ください。
京都総合法律事務所に寄せられるご相談例
京都総合法律事務所では職務怠慢な社員に関して以下のようなご相談に対応が可能です。
- 能力不足の従業員について解雇を含めた対応を検討したい
- パフォーマンスが伴わない従業員の待遇を見直したい
- 特定の従業員にやめてもらいたいが、解雇ではなく円満に退職してもらいたい
- 能力に見合った給与体系に改めたい
- 仕事もないのに居残っていた従業員から残業代請求を受けて困っている
- 注意や指導をするとパワハラだといわれないか心配
- 欠勤や遅刻が多い社員の対応に困っている
- 休職と復職を繰り返してほとんど実働していない社員の対応に悩んでいる
- 会社として問題社員と思っている従業員から逆に訴えられてしまった
- 能力不足の社員がでてきた際に対応できるよう就業規則を見直したい
>>労務トラブルに強い京都総合法律事務所の「労務支援コンサルティング」についてはこちらを御覧ください

京都総合法律事務所は、1976(昭和51)年の開所以来、京都で最初の「総合法律事務所」として、個人の皆さまからはもちろん、数多くの企業の皆さまからの幅広い分野にわたるご相談やご依頼に対応して参りました。経験豊富なベテランから元気あふれる若手まで総勢10名超の弁護士体制で、それぞれの持ち味を活かしたサポートをご提供いたします。
法律相談のご予約はお電話で
土日祝:応相談