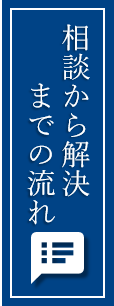懲戒解雇をした従業員に対しても退職金支払義務はある?

目次
退職金の不支給や減額は「当然」ではない
退職金規程を置いている多くの事業所では、功労があった場合に加算があり得るとする一方で、懲戒解雇事由があるときには、その全部又は一部を支給しないという定めが置かれていることが一般的です。
懲戒解雇は、普通の解雇とは違い、職場に対して迷惑をかけたり、問題を起こしたことから、明確に「罰」として解雇をするという意味合いが強いといえます。理由となった問題行動の大きさによっては、どうしても懲戒解雇という方法にこだわりたい、という場面も少なくありません。
このように懲戒解雇に罰としての意味合いがあるとすると、退職金を満額支払うことはスジが通らないのではないか、と思われることは極めてもっともなことといえます。実際、懲戒解雇となっても仕方のないようなことをしておきながら、退職金は満額支給を受けるということは、なんとも厚かましいとさえ思えることでしょう。
しかし、ことはそう簡単ではありません。裁判例上は、たとえ懲戒解雇となった従業員に対してでも、退職金をゼロにして良いということには、なかなかならないことが少なくないのです。こちらのコラムでは、このことについて解説をいたします。
そもそも退職金はなぜ支払うことなっているのか
かつて我が国の経済が右肩上がりで成長していた時代においては、長年勤め上げた後は、退職金と年金で悠々自適のシルバーライフを過ごす、ということが誰しもによって描かれているごく標準的な人生設計でした。
ここでは年功序列・終身雇用の雇用形態が前提とされており、いわば会社が従業員の人生を丸抱えすることが前提となっていました。こういう前提に立って設けられている退職金制度は、長年の功労に報い、退職後の生活を支えるという意味合いを持っており、退職金に関する基本的な考え方を示したとされる最高裁判例においても、「過去の功労」が考慮されているものと理解されてきました(最判昭和52年8月9日[三晃社事件])。
勤続年数が短かったり、勤務成績が悪い従業員については、過去の功労なるもの自体がそもそもあるのか、という疑問もあるところですが、そのような従業員であっても、一応、仕事をさせているわけですから、仕事をさせている以上、何らかの利益は会社に上がっていたであろうというのが裁判所の考え方です。
要するに、懲戒解雇によって辞めてもらわざるをえない従業員は、最後の最後で道を踏みはずしてしまったかもしれませんが、程度の差はあるものの、そうした決定的な問題を起こすまでは、一応「それなり」に仕事をしていた、とみられてしまうということです。
このように、退職金を過去の功労に報いるものと考えれば、最後の最後に起こした問題行動があったとしても、それだけで過去の功労の全部が帳消しになってしまうほどに大きなものでない限り、退職金を全く不支給とするのは、かえって理屈に合わないとするのが裁判例の基本的な考え方になります。
それでも退職金の不支給が認められる場合があるか
懲戒解雇とした従業員に対し、退職金を完全に不支給とすることができるか、それとも一部は支払わなければならないか、という問題について答えを出すための基準は、その理由となった問題行動が、過去の功労を完全に抹消してしまうほどのものとまでいえるかどうかということがポイントとなります。
しかし、事業主側からしてみると、過去にどれだけの功績があろうとも、雇い続けることはまかりならないと考えたからこそ、あえて懲戒解雇という選択肢をとったのであり、感覚的には、懲戒解雇になる以上は、過去の功労など完全に抹消されてしまうといえるのではないか、と思えるところです。実際、直近の裁判例においても、過去の功労と問題行動の重大さとを比較することは非常に困難であって、こうした判断基準自体が不適当であることを示唆した例もあります(東京高判令和3年2月24日[みずほ銀行事件])。
退職金の不支給や減額の当否が争われた例はたくさんありますが、そこでは過去の功労を完全に抹消してしまうほどの問題行動があったといえるかどうかという判断基準が用いられているものの、多くはその問題行動によって、具体的にどのような「実害」が生じたかということが問われています。
たとえば横領や背任のように、会社に対して金銭的な損害を与え続けたり、会社の重要な営業秘密をリークしたりしたような場合には、会社が被った実害をとらえやすく、そうした実害を被った以上、退職金全額の不支給もやむを得ないものとして認めた例もあります(大阪地判平成15年7月18日、前掲東京高判令和3年2月24日など)。
一方で、会社の業務と関係のない私生活上の問題行動の場合には、たとえそれが犯罪行為にあたるものであって、自社の従業員であると報道されたというような場合であっても、全額の不支給は認められないという傾向にあります(東京高判平成15年12月11日[小田急電鉄事件]など)。
社会的にも非難されるべき問題行動に及んだ従業員がいたとあっては、会社の評判にも関わることです。しかし、冷静に考えてみれば、従業員が会社の業務と全く関係のない私生活において問題行動に及んだからといって、会社が非難されることそれ自体がおかしいともいえます。このような場合は結局、会社の「実害」が生じたということ自体、感覚的なものにとどまるので、退職金全額不支給を肯定する方向には、なかなか傾きにくいといえます。
懲戒解雇した従業員の退職金問題への対応
退職金は、どのような要件でいくらを支払うかを明確に定めていてはじめて、従業員の権利となるものです。その裏返しとして、どのような場合には支払わないのかも定めておかなければ効力を有しません。懲戒解雇事由があったときに、退職金の全部又は一部を減額するということは、社内規程に根拠があることが大前提です(昭和63年1月1日基発第1号)。
また裁判例の中には、退職金に過去の功労としての意味合いだけでなく、賃金の後払い的な性格があるとして、最低限、この後払い的な部分については減額ができないとしたものもあります(名古屋地判平成6年6月3日)。
懲戒解雇した従業員に対しては、退職金の全部又は一部の不支給によって対応しようとする場合、その従業員がどれほど重大な問題行動を起こしたのかはもちろんのこと、会社に対してどれだけの「実害」が生じたかを具体的に立証できるよう、根拠を整えておくことが重要です。こうした根拠が客観的な証拠として伴わない場合は、退職金の全額不支給はもちろんのこと、そもそも懲戒解雇が裁判所でも通用するかどうか、慎重な検討を必要とします。
あるいは、問題行動があったことそれ自体は客観的な証拠から明らかであっても、退職金の額に比較して実害が小さかったり、そもそも客観的に示せる「実害」が見えにくい場合には、退職金の全部不支給ではなく、一部不支給にとどめた方が紛争リスク軽減のためには妥当であるといえます。
退職金の一部を不支給とする場合、どの程度までの減額であれば許容されるかは、全くのケースバイケースですが、最大でも7割を超えて減額することは、いざ紛争となった際には追加で支払いを命ぜられるリスクが高いといえます。
このように、従業員を懲戒解雇にしたとしても、退職金の全額不支給とすることには、裁判所としてはかなり消極的です。懲戒解雇をすることは、退職金の支給という場面においては、決定的な理由を伴うものとまではいえず、むしろあえて懲戒解雇としたがために、退職金の支給額だけでなく、解雇そのものの効力を争うという紛争がかえって生じてしまうおそれもあります。
問題行動のある従業員へ解雇をもって臨まざるを得ないという場合でも、どのような手順で対応を進めていくのか、また退職金はどこまで支給するのか、お悩みの際には、是非とも当事務所にご相談ください。
懲戒解雇をした従業員への退職金が支払われた事例
労働者を懲戒解雇する場合、退職金が不支給とされることは実務上よく見られますが、実は、全く支給しないで済むということは極めて例外的な場合に限られます。
今回は、懲戒解雇を有効としつつ、退職金の不支給を一部不適法とした事例を紹介します(東京地判令和2年1月29・判時2483号99頁)。
事案の概要
(1)本件の被告は株式会社みずほ銀行(以下、単に「銀行」といいます。)であり、原告は、約30年間、同銀行に勤務していました(期間の定めのない雇用契約)。
原告は、対外秘である行内通達等を無断で多数持ち出し、出版社等に内容を漏えいしたとして、懲戒解雇処分を受け、退職金約1200万円を不支給とされました。
(2)そこで、原告は、被告に対し、主位的に、懲戒解雇が無効であるとして、雇用契約上の地位確認及び未払い賃金(遅延損害金を含む)の支払いを、 予備的に、懲戒解雇が有効であったとしても、退職金の不支給は不合理であるとし、退職金(遅延損害金を含む)の支払いを求め、訴訟を提起しました。
解説
(1)懲戒解雇の有効性
ア まず、懲戒解雇は、就業規則において懲戒の種類及び事由が定められていなければ、そもそも行うことができないというのが判例の立場です(最判平成15年10月10日)。
被告の就業規則においては、懲戒解雇の定めがあり、また、懲戒事由に関する規定として、次のとおりの定めがありました。
第70条 職員が次の各号の一に該当するときは、情状によって、これを懲戒する(以下は、本件に関連する規定のみ)。
① 法令に違反し、またはこの規則その他諸規定あるいは業務上の命令に正当な理由なく従わないとき
② 職務上、職務外を問わず、会社またはみずほフィナンシャルグループの信用、名誉を傷つけ、または会社に損害を及ぼすような行為のあったとき
③ 経営上・業務上の秘密、業務上知り得た秘密、ならびに業務上知り得た個人情報を正当な理由なく漏らし、または漏らそうとしたとき
⑰ その他前各号に準ずるような行為のあったとき
なお、上記各号は、いずれも一般的な内容であり、就業規則においてよく見られる規定であると言えます。
イ 本判決は、原告の行為として、意図的な4件の情報資産の持ち出し及び15件の情報漏えいを認定した上で、これら各行為は、被告就業規則第70条1号乃至3号及び17号に定める懲戒事由に該当すると判断しました。
ウ さらに、従業員は労働者として労働基準法や労働契約法等の法律によ り、その権利が強く守られており、解雇についても客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないものは無効となることが法律で定められています(労働契約法第16条)。
そして、懲戒解雇は、懲戒として最も重い処分であり、被処分者の再就職の障害にもなるため、当該行為の性質、態様、被処分者の勤務歴、その他情状を斟酌し、解雇とするには重すぎるときは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないことから、懲戒解雇は無効になるとされています。
エ この点について、本判決は、㋐社外秘として管理されていた行内通達等を意図的かつ常習的に漏えいした原告の行為は、情報資産の適切な保護と利用を重要視する被告の企業秩序に対する重大な違反行為であるといえること、㋑原告の情報漏えいに基づき多数の記事が執筆されたことが推認され、これにより被告の情報管理体制に対する疑念を世間に生じさせ、被告の社会的評価を相応に低下させたといえること、㋒過去のけん責処分による反省もみられなかったことを総合すると、原告と被告との間の信頼関係の破壊の程度は著しく、将来的に信頼関係の回復を期待することができる状況にもなかったとして、懲戒解雇は客観的に合理的な理由があり社会通念上相当である、と判断しました。
(2)退職金不支給の適法性
ア 本判決は、懲戒解雇を受けた場合に退職金を不支給とすることができるのは、労働者が使用者に採用されて以降の長年の勤続の功を抹消ないし減殺してしまうほどの著しく信義に反する行為がある場合に限られると解するのが相当である、という判例の立場を確認しました。
イ その上で、本件について、原告の行為は、被告の企業秩序に対する重大な違反行為であり、被告の社会的評価を相応に低下させたものであるといえるが、被告のサービスに混乱を生じさせたり、被告に具体的な経済的損失を発生させたりするものではなかったことなどから、原告の約30年にわたる勤続の功を完全に抹消ないし減殺してしまうほどの著しく信義に反する行為であったとまでは評価することは困難であるとして、退職金の不支給は、7割を不支給とする限度で合理性を有すると判断しました。
まとめ
今回の裁判例をふまえると、重大な違反行為をした従業員を懲戒解雇する場合であっても、勤続の功を完全に抹消するほどの損失が会社に発生していない場合、退職金の全額不支給は認められない可能性が高いということになります。
どの程度の不支給であれば合理性が認められるかについては、懲戒事由とされる個別具体的な事情等にかんがみ、ケース・バイ・ケースの判断が必要になってきます。
懲戒解雇について悩み・不安・疑問等ありましたら、当事務所の経験豊富な弁護士が承りますので、是非ご相談ください。

京都総合法律事務所は、1976(昭和51)年の開所以来、京都で最初の「総合法律事務所」として、個人の皆さまからはもちろん、数多くの企業の皆さまからの幅広い分野にわたるご相談やご依頼に対応して参りました。経験豊富なベテランから元気あふれる若手まで総勢10名超の弁護士体制で、それぞれの持ち味を活かしたサポートをご提供いたします。
法律相談のご予約はお電話で
土日祝:応相談