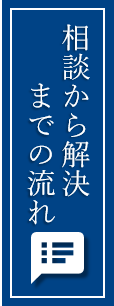普通解雇、自己都合退職、懲戒解雇の違いや取り扱いにおける諸注意について
「自己都合退職」と「会社都合退職」
いろいろな経緯があって、退職をすることになった従業員から、「会社都合退職にしてください」という申し出がなされることがよくあります。
会社都合退職とは、会社が従業員を解雇した場合のほか、会社が退職するようはたらきかけたことで、退職届を提出して退職する場合をいいます。
このような経緯で退職する場合、会社としては、「言われなくてもそのように扱います」ということになるでしょう。
従業員があえてこういう申し出をするのは、自分自身の都合で退職をしていながら、取り扱い上は「会社都合」として欲しいという希望によるものです。
従業員が自分自身の都合で退職をするのは、自己都合退職と呼ばれる退職方法であり、これを会社都合として取り扱うということは、実際には従業員が自分自身の都合で退職を申し出ていたのに、あたかも会社がその従業員を解雇したり、退職するよう働きかけたかのような、事実と異なる取り扱いをするということになります。
したがって、会社の立場からすれば、実際には「自己都合退職」であったにもかかわらず、「会社都合退職」として取り扱わなければならない理由はありません。
ところが従業員の立場からすると、退職の理由が会社都合か自己都合かは、雇用保険から失業給付を受ける際に大きな違いにつながってきます。
会社都合退職の場合、最短で7日間の待機期間の翌日から支給されますが、自己都合退職の場合、支給されるのは、どれだけ早くてもそこからさらに3ヵ月後になってしまいます。
その上、支給日数についても、会社都合退職の場合が最大330日間であるのに対し、自己都合退職の場合は150日間とこれも大きく違ってきます。
そのため、実際には自己都合退職でありながら、会社都合退職にして欲しいという申し出があるわけです。
きっかけは従業員からの申し出であったものの、その申し出がなければ、会社の方から退職勧奨をしていたような場合など、会社都合退職と取り扱っても、必ずしも事実と異ならないような場合には、従業員の生活保障を考えて、あえて会社都合として取り扱うという方法もないわけではありません。
しかし、会社において何らかの助成金の支給を受けている場合は要注意です。
会社都合退職があったことは、多くの助成金において支給制限事由となり、場合によっては支給を受けている助成金を返金しなければならないこともあるからです。
もっぱら従業員が自分自身の都合で退職したにもかかわらず、会社都合退職と扱うことは、十分慎重にならなければなりません。
「普通解雇」と「懲戒解雇」
会社都合退職にあたる典型的な例は「解雇」による場合です。そのほかには、会社から従業員に対して退職するよう働きかける「退職勧奨」による場合も、会社都合にあたります。
退職勧奨の場合、会社から従業員に対して退職するよう働きかけたとしても、最終的に「退職届」が提出されれば、自己都合退職として扱えるのではないかと考える方もあるかもしれません。
しかし、自己都合退職は、あくまでも会社の意思と無関係に自分自身の事情で退職する場合をいうので、会社が退職して欲しいと申し述べている以上、退職届が出たからといって、これを自己都合退職と扱うことは正しくありません。
従業員を解雇しようとするときは、少なくとも30日前に予告するか、予告をしない場合には30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(労基法20条1項)。
ただし、この予告日数は、平均賃金を支払った日数分、短縮することができます(同2項)。この規定による予告の仕組みを解雇予告制度といい、これに基づいて支払われるものを解雇予告手当といいます。
従業員の立場からすると、急に解雇を言い渡されるとたちまち生活に困ってしまうので、解雇に予告が必要であることはある意味当然であるといえます。
しかし、会社の立場からすると、あまりに許され難い問題行動に及んだ従業員について、即時に解雇できず、もし即時に解雇したいのであれば、平均賃金30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならないというのは、納得できないところです。
あまりに許され難い問題行動に及んだ従業員に対しては、通常の解雇とは異なる懲戒として解雇する場合があり、この懲戒解雇によるときにまで解雇予告義務を課されないとするのが法律の立場です。通常の解雇は、懲戒解雇と区別して普通解雇と呼ばれるのが一般的です。
そこで解雇予告義務を免れ、解雇予告手当なしに即時解雇をしようという目的から、懲戒解雇が行われる例がしばしばあります。
しかし懲戒解雇は、就業規則において懲戒の種類及び事由が定められていなければ、そもそも行うことができないというのが判例の立場です(最判平成15年10月10日)。
また就業規則に定めを置いていても、懲戒手続について就業規則に詳細に定めている場合には、これを漏れなく行っていなければなりませんし、懲戒解雇に該当する事由があったことも証拠によって証明しなければなりません。
なおかつその事由があった場合で、懲戒解雇とされることが社会通念上も相当といえなければなりません。それだけでなく、解雇予告義務を免れ、解雇予告手当なしの即時解雇を有効に行うためには、労働基準監督署から除外認定と呼ばれる認定を受けなければならず、この認定自体、容易に受けられるものではありません。
このように解雇予告手当なしに即時解雇しようという目的から、懲戒解雇を行ったとしても、その目的を達成できない場合が少なくありません。
それだけでなく、就業規則上の懲戒解雇事由に厳密には当たらないとされたり、形式的には当たったとしても、懲戒解雇は重すぎるとして、解雇無効の判断がなされる可能性さえあります。
それでもなお、懲戒解雇にこだわる必要性は、多くの会社で懲戒解雇が退職金の不支給又は減額事由とされているという点にあります。
ところが就業規則に定めを置いていたとしても、懲戒解雇をした従業員の退職金を不支給とできるのは、懲戒事由となった問題行動が、永年の功労を抹消してしまうほど著しく不誠実であったことを要するとするのが判例の立場であり、全く支給しないで済むということは極めて例外的であるといえます。
ただし、懲戒解雇自体が有効であると認められる事例では、退職金について相応の減額は認められることが少なくないので、退職金の支給との関係では、普通解雇によらず懲戒解雇によることに重要な意味があり得ます。
関連記事
従業員の退職時に思わぬ法的トラブルに至らないために
貴重な人材が退職のやむなきに至ることは、多くの場合、会社にとっても損失です。しかし、問題のある従業員については、むしろ雇用を継続し続けることの方が、長期的には会社にとっての負担となることから、解雇を決断せざるを得ないこともあるかもしれません。
しかし、「許せない」との強い思いで解雇をしてしまったり、就業規則との整合性を確認しないで懲戒解雇に踏み切ることは、後々、大きな法的トラブルへと発展しかねません。
また、もっぱら自己都合退職であるにもかかわらず、従業員によかれと思って会社都合退職として取り扱うことは、過去の事実経過を曲げてしまうことになり、あたかも会社が従業員を解雇してしまったかのようにとらえられてしまい、労務トラブルの元となるだけでなく、助成金の支給制限を受けるなど、より大きな経営リスクまで生じかねません。
少しでも「立つ鳥跡を濁さず」といかない兆しのある従業員の退職には、思わぬ法的トラブルが潜んでいるかもしれません。
会社側の立場からの労務問題に注力している当事務所へ是非ともご相談ください
>>労務トラブルに強い京都総合法律事務所の「労務支援コンサルティング」についてはこちらを御覧ください

京都総合法律事務所は、1976(昭和51)年の開所以来、京都で最初の「総合法律事務所」として、個人の皆さまからはもちろん、数多くの企業の皆さまからの幅広い分野にわたるご相談やご依頼に対応して参りました。経験豊富なベテランから元気あふれる若手まで総勢10名超の弁護士体制で、それぞれの持ち味を活かしたサポートをご提供いたします。
法律相談のご予約はお電話で
土日祝:応相談